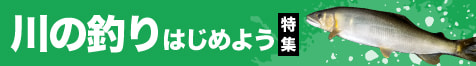テンヤで楽しむ船タチウオの基礎をご紹介!
ここでは、基本となるタックルや仕かけ、エサ付けや誘い方などをお届け!
タックルと仕掛け
竿は、タチウオテンヤと銘打たれたものなら、全長2m前後のショートタイプが主流。調子は大きく掛け調子と食わせ調子に大別される。
掛け調子は軽くて持ち重りせず、穂先の感度がよい8対2や9対1調子の物などを選ぼう。巻き上げやストップなどの誘いをひん繁に繰り返し、小さなアタリも掛けアワせていく人向き。
食わせ調子は、電動のスロー巻きで誘い、大きく食い込ませてからアワせる人向き。しなやかに曲がり込むので食い込みはよい。
軽量で持ち重りのしない小型の両軸(手巻きまたは電動)リール。タナ合わせが重要なので、初心者はカウンター付きのものを使おう。

ダイワの「アドミラA」
PEラインのタカ切れも考慮に入れて、深場でも対応できるようにラインを200~300m巻けるものが主流になっている。
PE2号が200m以上巻けるラインキャパの小型電動リールは、深場でも快適に釣れるのでオススメ。船宿によっては、PE〇〇号以下など統一していることも多いので確認を。
タチウオテンヤは、ヘッドの形状、カラーなど各社さまざま。
大阪湾周辺の船宿ではオーソドックスな1本バリタイプのみを使用することが多い。リーダーはフロロが主流。テンヤのオモリの号数は、大阪湾では船宿によって統一されていることが多いので、予約時にはテンヤの号数やハリスなどを確認しておこう。
仕掛けのアピールを高めるためのケミカルライト。サイズはさまざまあるが、船釣りで使う場合は50mmが大半で、大きくても75mmまでにしておこう。
あまり大きいと、潮の抵抗を受けて仕かけがなびくのでオマツリの原因になる。
船宿によっては、そういった理由から光りモノや装飾アイテムをラインに付けることを禁止している所もあるので、必ず船宿に確認しておこう。

エサの付け方
エサは主に冷凍イワシ。地域によってはサンマやコノシロ、オオナゴを使ったりすることもある。
イワシのサイズに応じて尾がテンヤからはみ出すように、軸に沿って真っすぐ剣に刺す。
次に、針金でイワシを巻く。注意点としては、頭の方をしっかりと巻いて固定し、徐々にお腹の方へズラしていく。
お腹はイワシがズレない程度に数回巻けばOK。
針金は、ハリ軸の一番後ろの剣を目安に折り返し、ヘッドの所で留める。
針金が長いと手返しが悪くなるので、長い場合は切るか、テンヤのヘッドの後ろの軸に巻いておくとよい。

①針金をよけて、イワシは曲がっていれば真っすぐに伸ばす

②ハリの軸に沿って、真っすぐにイワシをセットする

③頭をしっかり巻き、お腹はズレない程度に巻く

④軸から出る剣の最後の位置で折り返して巻く

⑤最後に頭の部分に巻いてハリの軸の部分にねじって留める

イワシの尾が出ているのがポイント
ちなみにサンマの場合は、3枚に下ろした身を塩で締めておき、付ける時は身で少し針の軸を包むようにして、針金で巻くとよい。サンマは持参になるが、エサ持ちがよいのが特徴。

基本的な釣り方と誘い
ポイントに着いたら船長から仕掛け投入の合図が出される。
慣れないうちはテンヤを竿下に、少し慣れてくれば周囲のラインの位置を確認してアンダーでキャストして潮カミに投入しよう。

仕掛けを入れたら、リールをフリーにした状態でテンヤを底まで下ろそう。
ただし船長から「〇〇mからやってみて」と指示があった場合はそのタナまで。
着底してラインがフケれば、すぐに糸フケを取ってから2~3m巻き上げる。
ここからが、いよいよ誘い開始だ。
定番の誘いはいくつかあり、またそれらの組み合わせなどバリエーションは人によってさまざま。
ここでは基本的な誘いパターンをご紹介。

タダ巻き
文字通り、ただ巻くだけだが、巻く速度を変えることによって活性の高いタチウオにも、低いタチウオにも対応できる。
電動リールなら指示ダナ間を探る度に巻き上げ速度をかえていけば、タチウオが反応する速度を見つけやすい。
ストップ&ゴー
「巻き」と「止め」を交互に行う「ストップ&ゴー」。基本的には、タダ巻きよりも速いテンポの釣りで使うことが多い。
この誘いも、巻き上げ距離(およそハンドル1~5回転)と止める時間(およそ3~10秒)に変化を付けていけば、数種類の誘いパターンができる。
基本的には活性が高ければ巻き上げ距離を長く、止めは短く、活性が低ければ巻き上げ距離を短く、止めを長めにしてみよう。
ジャーク
竿でシャクリを入れながらリールを巻いて誘う釣り方。
竿を1回シャクってリールのハンドルを1回転させるワンピッチジャークが基本で、1度の誘いサイクルは2、3回ワンピッチジャークを入れて、ピタっとステイさせる人が多い。
タチウオの活性に応じて、シャクリ幅、速度、リールで巻き上げる距離(タチウオの追いが悪い時は1度のシャクリで1回転させずに半回転やそれ以下)、ステイの時間をかえる。
基本的には…
・活性が高い時→シャクリ幅を大きく、速く、ステイは短めに
・活性が低い時→シャクリ幅を小さく、ゆっくり、ステイは長め
もちろん当日の状況により異なるが、基本は上記のイメージ。
アタリがでれば、即掛けタイプの人ならそこで合わせるとよいが、食わせるタイプの人なら同じようにジャークを続ける場合は移動距離(シャクリ幅、リールで巻き上げる距離)を少し短めにして追わせるか、そこからスローな巻き上げやストップ&ゴーにしてしっかりと追わせるとよい。
アワセのタイミング
タチウオのアタリは多彩だが、始めはエサを突くように、コツ、コツ…と小さなアタリが竿先にでることが多い。
ベテランはこのアタリでも掛け合わせていく人もいるが、ビギナーなら小さな前アタリは見送って、そのまま誘い続けよう。

タチウオがエサを追ってくれば、次第にハッキリしたアタリがでてくる。
グンと力強く竿先を押さえたり、大きく舞い込むアタリが出れば、テンヤのハリを掛けるようにすかさず竿先を上げてアワせよう。

また、急にテンヤの負荷が竿先からなくなるような時(フッと軽くなる感じ)は、タチウオがテンヤを下から食い上げている。
こんな時は、すぐにアワセを入れればハリ掛かりの可能性が高い。
取り込み
アワセを入れてハリ掛かりすれば、リールを巻き始める。
電動リールの場合は、いきなり全速で巻くとバレることも多いので注意。巻き上げ中はラインのテンションを緩めないようにしよう。
少し速めの一定の速度で巻き上げ、竿を立てて竿の弾性をしっかり利用してテンションを保とう。

また、巻き上げ途中に急に負荷がなくなる時があるが、これはタチウオが上に向いて泳いでいるので、より速く巻き上げよう。
タチウオが水面まできたら、ラインを緩めないように注意しながら、リーダーをつかんで抜き上げよう。

竿にタチウオが付いている状態で船内に抜き上げると、万が一ハリが外れると反動でテンヤが周囲の人にぶつかったり、ハリが刺さってしまう事故も考えられるので、リーダーをつかんで抜き上げること。