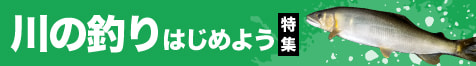和歌山・串本のカセでは、例年秋から春先まで青物を狙うことができる、青物好きにはタマらない釣り場だ。秋頃はハマチ級が多いが、冬から春にかけては10kgオーバーのブリも期待できる。

ここでは、ブリが狙える有望ポイントのひとつである、「センカイ40m」から狙う、青物のタックルやエサの付け方、釣り方、そしてコツなどの攻略術を紹介したい。
自由きままに楽しめる「カセ」の魅力
カセとは、ボートのことで、養殖筏やアンカーで船を固定して釣るため、船の免許は不要だ。串本のカセは、季節によって魚種多彩に狙え、また自由なスタイルで釣りを楽しむことができる。

センカイ40mのカセ。カセは養殖筏に固定しているため、釣りは片側のみでしかできない

センカイ40mのカセから見る風景。目の前には、くしもと大橋が見える
タックル&仕かけ
ロッドは、オモリ負荷80号程度の7対3調子の船竿。青物専用と記載しているタイプがよい。兼崎氏は、磯竿5号を使用していた。リールはカウンター付きのフロロ8~12号を100m以上巻けるものがよい。

道糸は、フロロ通し8~12号。10号を基本に、大型が釣れている場合は12号、食いが渋い時のために8号を用意しておくのがベター。青物はラインの太さで食いが大きくかわる。針はヒラマサ針15号前後でよい。
基本的には、ハリスと針だけのシンプルな仕かけだが、潮が速い場合は状況に合わせてガン玉を付けよう。付ける場合は、針から矢引き程度上でよい。



針は、ヒラマサ針15号程度がよい。オススメは、がまかつの「ジーハードV2 V2 ヒラマサ」

出典:がまかつ
エサは冷凍イワシを使用
①頭の少し後ろの背から針を通す
②中骨を挟むようにして腹の真ん中に針を刺す
③針先を少し出せば完成。

イワシはまず背に針を通してから、中骨を挟むようにして、腹の真ん中から針を出す
基本的には上記の付け方でよいが、食いが渋い時やエサが残る時には、頭と尾の方を切り、さらに2分割にしてブツ切りにするのもよいほか、3枚に下ろして切り身にするのもよい。
よくやってしまいがちなのが、目に通した後に背に刺し通すやり方。これは食いがあまりよくないため、オススメしない。
マキエ、サシエに使用する、冷凍イワシは1人最低1枚は必ず用意しておこう。

基本の釣り方とコツ
①オモリを使い、タナを取る
②マキエを撒く
③仕かけを入れる
④タナまで入れたらステイ
③誘い(竿をゆっくり大きく上下する)
④アワセは竿が舞い込んでから
⑤やり取り

まだ暗い間は、20~30mのタナがオススメ。日が上がってからは、青物は底に沈むため、タナは底から3m以内が基本。
マキエは、3分に1度は撒こう。特に暗い間は、どれだけしっかりとマキエを撒けるかが、釣果を伸ばすカギなので、撒くのを惜しまないように!
現場の生情報 釣果を伸ばすワザ
筆者が釣行した時は、潮がかなり速く、仕かけはオモリ5号を付けないとタナまで入らないほか、マキエが流れて全く効かない状況だった。
そこで大島フィッシングの常連である兼崎氏が取り出したのが、ペットボトルの底を切り、底付近にオモリを付けた底撒きアイテム。
これのおかげで、タナにマキエを撒くことができた。

当日は、底でマキエを効かすことができるかが、釣果を伸ばせるカギとなり、ほかの人の竿が曲がっていない間も、兼崎氏はコンスタントに釣果を伸ばすことができた。
底撒きアイテムがない人は、天ビンズボ釣りで狙うのもよい。その際は、1本針でハリスを2ヒロ程度取るのがベター。状況に合わせて、さまざまな引き出しを持っておくことが大切だ。
■取材協力:大島フィッシング