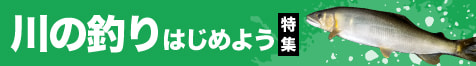今回は人気沸騰中の”アマラバ”を釣果とともに解説
タイラバ釣りをしていると、アマダイがヒットしてくることがある。
マダイの仲間ではないが、マダイより遥かに高価で、キロ1万円の値が付くこともある。

だから、思わぬ〝外道〟に小躍りして喜ぶアングラーも少なくない。
旬は寒風吹き荒ぶ11月から翌年の3月頃だ。
ウロコを引かずに背開きにし、ひと塩振って身を閉じ、浜で一昼夜寝かす。
そうして京都へ運んだものは「若狭ぐじ」と呼ばれる京料理の華だ。
アマダイの語源はその甘い味わいに由来するとか、ひょうきんな横顔が頬被りをした尼僧に似ているから「尼鯛」とも。
ちなみに香港周辺では広東語で「馬頭(マータウ)」と呼ぶから、やはり風貌に由来するのかもしれない。
近頃は「タイラバ」ならぬ「アマラバ」と称し、高級魚のアマダイをタイラバで狙うアングラーも増えてきた。

この釣りが初めて誌面に紹介されたのは、2014年ソルトワールド109号(12月号)で、筆者の丹後半島沖での釣行が巻頭グラビア6ページに渡り、紹介された。
さらに2017年同誌123号(4月号)に「新しい分野となるアマダイ狙いのラバージギング」として、能登半島富来沖のアマラバ釣りを解説。
それから早や5年が経つ。
その間に試行錯誤を重ね、ゲームフィッシングとしてアマラバ釣りが各地で確立されてきた。
2月初旬、今年も良型のアマダイが富来沖で釣れ続いていると連絡が入った。
和歌山沖でアマラバ釣りのさらなる釣技向上を探求する、海南の遊漁船KAISHINの神田泰志船長をお誘いし、2人で富来を目指した。

「富」が「来」るという縁起のいい名前の漁港は、古来よりブリやヒラマサなどの青物をはじめ、マダイやアマダイ、中深海のアカムツなどの高級魚が水揚げされ、文字通り豊かな町であることが伺える。
かれこれ15年ほど前から、ジギングやマダイのラバージギングで筆者が釣行を重ねてきた海域だ。
2016年の春に乗っ込みの大ダイ狙いの実釣会を富来港の「遊心丸」で開催したのが、佐野裕幸船長と出会ったキッカケだった。
ニッカポッカがトレードマークの佐野船長は「キロアップの大きなアマダイがタイラバで釣れるよ!」と笑顔で語っていたが、言葉通りの釣果に、ド肝を抜かれた。
アマダイの棲息域は日本海側は青森県津軽海峡から九州西岸まで、太平洋沿岸は千葉県外房から九州南岸と東シナ海、瀬戸内海と広範囲に及ぶ。
アマダイは貝殻まじりの砂泥地を好む魚であり、自らが入る巣穴を掘ってそこに棲息する。
巣穴は崩れない泥質であることから、タイラバが着底すると、ズボッとめり込むような感触の底質になる。
アマダイは巣穴から頭を出していて、エサとなるエビや小さいカニなどの甲殻類、小魚が近寄ると巣穴から飛び出して捕食する。
漁場としては、潮通しがよく、地形的に潮流の流路となる谷筋の斜面がアマダイの好漁場だ。

はえ縄の漁師たちは、こうした漁場を熟知している。
6時に港に集合し、6時半出船。船は70ftの大型船、多少の風波でも安心して釣りができる。
15分ほど走り、最初の漁場に到着した。
佐野船長は遊漁船を始める前は富来港で漁師をしており、アマダイの漁場や釣り方に精通しているのが心強い。
ドテラで広範囲を探るのが遊心丸の釣り方だ。
この日、アマラバ乗合船には8人が乗船し、全員が右舷に並んだ。
私のポジションは右舷の大ドモだった。
私はアマダイに効くというグリーンのカーリーネクタイを選び、金龍鉤の「鯛ラバ専用アシストフック 喰わせ鈎(ネムリ型バーブレス)」のシングルフックをセット。
はえ縄漁では大きくネムッた針を使用しており、アマダイにもネムリ針が有効である。
船中ファーストヒットは私にきた。
タイラバが着底後、ハンドル2巻き目で、竿先がゴンゴンと激しく絞り込まれる。
巻き上げているうちに急に大人しくなり、宙層で再び暴れ出す。
そして船縁でもう1度暴れるというのが、典型的なアマダイのファイトのパターンだ。

船長のタモに収まったのは、50cm近い良型のアマダイだった。
それも橙黄色のボディが美しい。
神田泰志氏もグリーンのネクタイをセットし、首尾よくアマダイをゲット。

富来沖のアマダイはネクタイカラーに極めてセレクティブ、この日の当たりカラーはグリーンとピンクだけだった。
グリーンもちょっと深みを帯びたカラーがよく、このカラーを持ち合わせているか否かで、釣果が別れる。
ピンクは、やや赤みがかったもので、甘エビがベイトなのかも知れなかった。

富来沖のアマダイの魅力は、何しろ大きいこと。
1kgを超えるサイズがまじるから驚く。
ちなみに、アカアマダイの極限体長は約60cm弱で推定年齢は15歳と言うから、優に10歳は超えるものと思われる。
佐野船長によれば、「肉質がよくて最高級魚と言われるシロアマダイの60cm超え、3kg級も釣れる」と言うから、富来沖の漁場はスゴイ。
この日、ご一緒した常連の東山政人氏の釣果が圧巻だった。
ピンク系のネクタイで通し、1人で10尾の良型のアマダイをゲット。

東山政人氏はピンクのネクタイのみを使用し釣っていた
それも、全てスピニングタックルである。
佐野船長は「投げて釣る方が絶対に有利だ」と言う。
水深が60mあっても、スピニングタックルで100~120gのタイラバを船が流れていく方向にキャストし、広範囲を探る。
数回巻いては落とし直し、船の真下になったら、回収して再びキャスト。
大ドモで船長のスピニングタックルと私のベイトタックルで釣り比べたところ、スピニングの方がアタリも多く、有利だった。
スピニングタックルはぜひ準備していくべきであろう。
船長に誘い方を伺うと、「アマダイは砂の中に潜っているので、タイラバが着底したら、トンッ、トンッと2回ほどボトムを叩き、砂煙を立てる。アマダイは興味を持って穴から出てくるので、あとはハンドルを5、6回ほど巻いて、ステイさせる。ステイしていても、船は潮流で流されているので、その間にアタックしてくる」と言う。
だいたいボトムから5mくらいのレンジを探れば十分とのことで、巻きのスピードは早めがいいと言う。

マダイも狙おうと思うなら、この砂煙り釣法はオススメしないと言う。
マダイのアタリと異なるのは、トンッ、トンッと叩いている時に、引っ手繰るようなアタリがきたり、ステイしている時に、ロッドを引き込むアタリである。
マダイと比較すると、さまざまなヒットパターンがあって、それが面白かった。
アマダイのタックルについては、基本的にはマダイのラバージギングと同じものでよい。
ロッドはベイトロッドはMクラス、スピニングならばMHクラスがオススメだ。
PEラインは、アマダイだけであれば、その引きと重量から0.6号で十分だが、富来沖の海域は、外道に大型の青物もヒットしてくる。
ほかの釣り人に迷惑をかけないためにも、船長は1.2~1.5号を推奨している。
スピニングも120gのタイラバをキャストするので、1.2~1.5号がよいとのこと。
魚影が濃いので、あえて細いPEラインを使用する必要はない。
アマダイの持ち帰り方法

アマダイは水圧の変化に弱く、釣り上げると腹部が膨張して死んでしまう。
釣り上げたらすぐに絞めて、血抜き、海水を浸した氷で冷やす。
アマダイの身は柔らかいので、持ち帰る際は魚体が重なったり、氷などが上にならないように注意する。
魚を冷やしたら海水を抜き、氷の上にスポンジやマットを敷き、その上に魚を並べて持ち帰ると、身が痛まない。
オススメのレシピは松笠焼き

フライパンにオリーブオイルを引き、ウロコを下にしたまま低温でじっくり焼き上げる。
ウロコがパリッと香ばしく、超美味。
写真はイタリアン風(多幸屋、大阪福島)