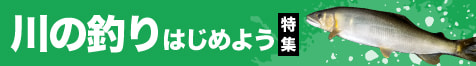竹村勝則 プロフィール
大阪湾のサヨリ釣りは、春から初冬までが釣期だが、来たるべきシーズンのために仕かけ、釣り方などを解説しよう。

サヨリはあのスマートな魚体に、クチバシのように伸びた下唇に口紅を付けて、眼が大きく愛らしい魚。針に掛かると大きく左右に走り回り、テールウォークまで見せる。魚体に似合わず猛ファイトを見せてくれるのが、醍醐味だ。
サヨリは外海にもいるが、だいたいは瀬戸内海や、大小の湾内に多くいて、上層を群れで泳ぐ魚。群れが回遊してくると、水面にポツポツと波紋が出て、キラッキラッと銀鱗が光るので、よく分かる。釣れるサヨリのサイズは20cm前後から30cmぐらいまでが多い。
サヨリの釣り方は、遠投カゴ釣りと、ノベ竿やリール竿を使ってのウキ釣りがある。
今回は、その中でも、遠投カゴ釣りの釣り方を紹介する。

竿はリール竿の2号から3号の4.5~5.3m。スピニングリールの2000番か3000番に、道糸は2~3号。
仕かけは、サヨリ専用の市販品がある。その仕かけはマキエを入れるプラカゴがあり、その先に発泡の玉ウキが3つほど付いており、その先にハリスと針がある。
仕かけが絡まないように、ハリスまでは太糸が付いている。

サヨリのアタリは、1番先のウキで見る。
サヨリ釣りのベテランは、仕かけをいろいろ工夫しているが、筆者もあれこれと仕かけ作りをしている。その1つを上の図で紹介する。
サヨリは目がよい魚なので、ハリスはなるべく細くする。普段は1号でよいが、食いが悪い時は0.8号か0.6号にするのがよい。ハリスの長さは、アタリウキから40~50cmでよいが、食い渋る時は60cmぐらい長くしてみる。
市販の仕かけは、さすがよくできている。カゴからアタリウキまでが短いものが多く、魚影が濃い時は、この方がよく釣れる。
しかし、食い渋る時はカゴからアタリウキまでが少し長い方がよい時が、ままある。
そこで筆者は、短くて60cm、長いと100cmぐらいにしている。
アタリを見る玉ウキは小さいほどよいが、遠投するとよく見えないので、玉ウキの直径が23mmぐらいのものを付けている。さらに遠投する時などは、30mmぐらいのものを付けている。

出典:がまかつ
針はサヨリ針の4号、5号でよいが、筆者はヘラ釣りのスレ針、アスカ2、3、4号を魚の大きさによって使い分けている。
スレ針はモドリがないので、エサが刺しやすいのと、針が外しやすい利点がある。針にモドリがないとバレやすいのでは? と思われがちだが、テンションを緩めない限り、バレは少ない。
サヨリは上層を泳ぐ魚なので、マキエは軽いものがよく、1番効果的なのが、アミエビ。そのアミエビに米ヌカをまぜると、さらに効果的。その割合は、だいたいだが、アミエビ3、4に米ヌカ6、7ぐらい。
カゴに入れる場合は、水分はやや少なめに。上から撒く時は水分は多めに練る。
サシエはサヨリ用のサシアミか、Sサイズのオキアミを使うが、遠投する場合は抜け落ちたりすることもあるので、イカの身を小さく切って使うと、エサ持ちがよく、1つのエサで2、3尾は釣れる。
サヨリは酒のアテが好きなのか、イカの塩辛が好エサのようなので、1度お試しあれ。


先にサシエを付けるか、カゴにマキエを入れるかは自由だが、後方に誰もいないかを確かめてから、仕かけを投入する。
仕かけが着水寸前、リールのスプールに手を当てて出るのをセーブして止めると、仕かけがまっすぐになって絡まない。
仕かけが着水したら、すぐに糸フケを取り、竿を2、3回シャクって、カゴからマキエを出す。そのマキエが散らばった所まで仕かけを引いて、サシエとマキエを同調させる。これが1番のコツ。
その後は、仕かけをスーッ、スーッと、一直線に数回引いて、マキエの筋を付ける。それを繰り返す。
サヨリは回遊性でもあるようで、初めは全く釣れなくても、マキエを続けているうちにやってくるものだ。
サヨリが集まってくると、水面にポツポツと波紋が出て、キラキラと魚体が見えだし、中には飛び跳ねたりする。そうなれば、シメたもの。

サヨリが食い付けば先端のアタリウキにでる。そのアタリは、ウキが左か右に動くことが多い。それ以外にも、何かウキが変だなと思ったら、合わせてみる。
居食いしていることもよくある。と言うのは、サヨリはエサを食って、ジッとしていることがよくあるからだ。
それと、仕かけが着水した後すぐに、サヨリが飛び跳ねることがよくある。これは、エサに食い付いて跳ねていることもあるので、すぐにアワセを入れる。

サヨリはピチピチ跳ねる元気者だけに、掴みにくいが、素手で掴むとウロコがいっぱい手に付いて、なかなか取れない。魚バサミを使うのが1番よい。
サヨリの釣り方で1番面白いと思われる、ノベ竿とリール竿のウキ釣りの紹介を後編として、次回紹介する。