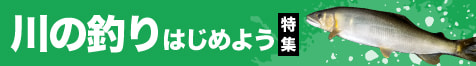磯や堤防、漁港を訪れると、岩場や壁面を高速で走り回る、あの生き物。「フナムシ」です。その見た目と素早い動きから「海のゴキブリ」という不名誉な呼ばれ方をされ、群れでいる姿に苦手意識を持つ方も多いかもしれません。
しかし、地味で嫌われがちなフナムシですが、その生態は非常に興味深く、釣りエサとしては驚くほど優秀な実力を秘めていることをご存知でしょうか。
今回は、意外と知られていないフナムシの本当の姿と、その活用法について詳しくご紹介します。
フナムシの正体はゴキブリではなく「甲殻類」

まず最も重要な点として、フナムシはゴキブリ(昆虫)とは全く異なる生き物です。生物学的には「甲殻綱・等脚目・フナムシ科」に分類され、エビやカニ、そして陸に住むダンゴムシやワラジムシに近い仲間なのです。
よく見ると、硬い甲羅に覆われた体やたくさんの脚など、エビやカニと共通する特徴が見られます。正面から見たときの、つぶらな瞳が意外と可愛いという声も。
日本には3種類のフナムシが生息
一般的に「フナムシ」として一括りにされていますが、近年の研究により、日本には主に3種類が生息しているのだとか…。
所詮フナムシはフナムシだろ、という声が聞こえてきそうですが、豆知識として(笑)。
フナムシ (Ligia exotica): 日本の広範囲に分布する最も一般的な種。
キタフナムシ (Ligia cinerascens): 主に北海道や東北地方の日本海側など、より寒い地域に生息。
ヒメフナムシ (Ligia miyakensis): 南西諸島などの暖かい地域に分布する小型の種。
普段私たちが見かけるのはほとんどが「フナムシ」ですが、地域によっては違う種類に出会っているかもしれません。
フナムシは、生態系において重要な役割を担っています。
藻類やプランクトン、生物の死骸、釣り人がこぼしたエサまで、何でも食べる雑食性です。彼らのおかげで、海岸はきれいに保たれており、まさに「海の掃除屋」と呼ぶにふさわしい存在です。

イワガニやイソガニなどのカニ類、イソヒヨドリやサギといった鳥類に狙われます。また、海に落ちた個体は格好の餌として魚たちに捕食されます。食物連鎖の中では、捕食される側として重要な位置を占めています。
海岸だけでなく、塩分濃度の低い河口域にも適応できる高い順応性を持っています。しかし、意外にも泳ぎは得意ではありません。波にさらわれると溺れてしまうことも多く、敵に驚いてジャンプした拍子に海に落ち、そのまま魚の餌食になる…というおっちょこちょいな一面も持ち合わせています。
フナムシをエサにすると、以下のような様々な魚を狙うことができます。

クロダイ(チヌ)
メジナ(グレ)
シーバス(スズキ)
カサゴ、メバルなどのロックフィッシュ
イシダイ、イシガキダイ
カワハギ、ベラ など
特に、堤防の壁際(ヘチ)に落とし込んでいく「ヘチ釣り」や「落とし込み釣り」では、自然に落ちてくるエサを演出できるため、絶大な効果を発揮します。
雑食性のフナムシは、食用には全く向いていません。そらそうだ…。
何を食べているか分からず、衛生上の問題や、寄生虫がいる可能性も否定できません。美味しいという話は聞かれませんので、食べるのは絶対にやめましょう。
「海のゴキブリ」という不名誉な愛称とは裏腹に、フナムシは生態系を支える重要な役割を持ち、釣りにおいては万能エサにもなる、非常に興味深い生き物です。
その見た目だけで判断せず、彼らの本当の姿を知ることで、次から海岸で見る目も少し変わってくるかもしれません。釣りの際には、ぜひ「特効エサ」としてフナムシの力を試してみてはいかがでしょうか。