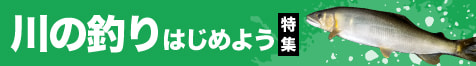全国的に高い人気を誇る船のイカ釣り。
船イカ釣りで狙えるターゲットは大きく分けて3種類。「マイカ(ケンサキイカ)」、「ヤリイカ」、「スルメイカ」の3種類がメインターゲット。
ヤリイカは冬がメインの釣期ですが、マイカは初夏から秋まで。年により年末まで楽しめることも。小型のスルメイカは4月末から初夏までがメイン。大型のスルメイカはオールシーズン楽しめます。
特に鉛スッテとドロッパーを使った「イカメタル」は、人気が年々うなぎ上りです。
それに加えて、最近人気急上昇なのがシンカーとエギを使用した「オモリグ」の釣り。
そこで今回は「イカメタル」、「オモリグ」の2つの釣法に加えて、伝統的な釣法である「胴突き」の釣りを合わせた、3つの船イカ釣りの基本を紹介します。
イカメタルの基本はコレ

・タックル&仕かけについて

タックルはイカメタル専用ロッドに両軸もしくはスピニングリール。メタルスッテ10~30号にドロッパーを1~2本。多くの船宿ではドロッパーひとつまで。なのでドロッパーをふたつ使いたい場合は要確認です。
・ロッド選択
イカメタルのタックルはベイトタックル、スピニングタックルの2つが存在しています。

ロッドの長さは6ft~7ft前後が多いです。
ショートロッドは操作感に優れており、レングスの長いロッドは波のある日でも揺れを吸収してくれるので仕かけが安定しやすいというメリットがありますね。
スピニングリールはキャスト性能が高く、イカのタナが浅くなった時に、浅いタナをカーブフォールで長時間トレースしたりすることができます。

ベイトリールのイカメタルにおける最大のメリットは、カウンター付きリールを使用できること。
イカ釣りはタナ合わせが非常に大切だからです。

ロッドパワーはXUL(エクストラウルトラライト)~MH(ミディアムヘビー)クラスまで様々ラインナップされています。
各メーカーによって使用できる範囲は異なりますが、まずはスッテが15~20号を快適に使えるロッドを選ぶとよいですよ。

メジャークラフトのクロステージCRXJ-B662M/NSは10~20号の鉛スッテに対応
リールはPE0.6号を200m以上巻けることが必要条件で、ギアは手返しを考慮してハイギアなモデルが有利ですよ。
・仕かけ

イカメタルの仕かけはメタルスッテと呼ばれる10~30号前後のスッテに、ドロッパーと呼ばれる浮きスッテや小型のエギを1つ付けるのが一般的。

鉛スッテ

タングステンのスッテは同じ重さでもワンサイズシルエットが小さくなるので、イカのサイズが小さい時や、手返しを上げたい時に活躍する
メタルスッテは鉛でできたものと、タングステンでできた高比重なものに分けられます。

浮きスッテ

小型エギ
ドロッパーの選び方は潮が流れている時は仕かけが安定しやすいエギタイプを、潮が流れていない時は浮きスッテタイプを選ぶとよいでしょう。
エギタイプはシンカーが付いているので、仕かけ自体の重量もあるので海中で安定しやすいためです。
・エダスの長さは?
イカメタルのドロッパーを付ける時のポイントにエダスの長さが挙げられます。
潮の流れや、イカの活性などに応じて使い分けるのがポイントですが、大きく分けるとショート、ノーマル、ロングの3パターン。
 出典:ダイワ
出典:ダイワ
ショートは高活性時などにドロッパーをキビキビ動かすのに向いています。
 出典:ダイワ
出典:ダイワ
スタンダードタイプはオールマイティに使えるので、まずはこの長さから始めて、当日の活性を見極めるのも◎。
 出典:ダイワ
出典:ダイワ
ロングタイプはイカのノリが悪く、エギやスッテのナチュラルな動きに反応してくる時にオススメですよ。
3タイプの仕かけを使い分けて爆ノリを目指して下さいね。
・スッテのカラー

スッテやエギのカラーはたくさんでていますが、実績が高い定番カラーは赤白、赤緑、赤黄などのカラー。
これらのカラーはマストですが、あまり同じカラーを続けるとイカがスレてしまうこともあるので、カラーは必ず豊富に持っておきましょうね。
また、夜光やブルー夜光、ケイムラなど発光するエギ、スッテもあるので種類は豊富に持っておきましょう。

ここからは、本格的な釣り方の解説をしていきます。
まずは、出船直後の明るい時間の誘い方から紹介していきましょう。
・ボトム近辺をネチネチと攻める

竿を大きく動かし過ぎず、ボトム近辺でエギ、スッテを跳ねさせるイメージで動かす
集魚灯が点く前、イカは基本的に回遊しており、回遊を待つ形になります。
また、タナはほとんどボトム付近になるので、底付近でシェイクをしてアピールして、ポーズでアタリを待つという形になります。
たまに何mか巻き上げてフォールを入れるのも有効な誘いですよ。
基本的にアタリがあれば全て合わせて下さい。
アタリはティップがグイッと入ったり、逆にテンションが抜けたり、もぞもぞと穂先に違和感がでたりします。
・集魚灯が灯れば

集魚灯が点くと、イカのベイトとなる小魚のタナが上がってきます。
それを捕食しようとイカのタナも上がってくるわけです。
船長が魚探を見て、ベイトの反応やイカのいそうなタナをアナウンスしてくれるので、まずはそのタナの5~10m下くらいから誘いを掛けてみましょう。
誘いは大きく分けて誘い上げと誘い上げに分かれますが、まずは誘い上げから解説していきます。

誘い上げで誘いを掛ける時は、1回のシャクリに対して1回転リールを巻く「ワンピッチジャーク」で2、3回誘ってステイ。
ほかには、巻きジャクリでショートピッチでハネさせるような誘いも有効です。
ステイ中にアタリが出るので穂先に集中して下さいね。
まずは、誘い上げで指示ダナの少し下ぐらいから誘ってみて下さい。
誘い上げに反応がなければ今度は指示ダナの上から誘い下げていきます。

誘い下げる時は竿一杯分上げてから竿で誘い下げていくとよいでしょう。
この時、フォールスピードを意識することも大切で、テンションフォールさせるのか、一気に竿を下げてフリーフォールさせるのか、反応を見て使い分けていきましょう。
集魚灯が点いてからも、アタリは即アワセでOK。掛からなかった場合は、その場でシェイクすると再びアタリがでることもありますよ!
オモリグ


・ロッド選択
ベイトロッドも一部発売されていますが、一般的なのはスピニングロッド。主にイカメタルよりも重いオモリを使うことから、より張りのあるロッドが好まれる傾向にあります。
また、キャストしやすいように少し長めの7ft前後のロッドがオススメです。

メジャークラフトのトリプルクロスとソルパラのオモリグモデル。パワーはXHで12~40号のオモリを使用することができる
リールは2500~3000番クラスでPE0.6号200mが巻けるハイギアモデルがオススメです。
・仕かけ

オモリグの特徴はイカメタルと違い、オモリが上部にあるということ。イカを掛けるためのエギはオモリに追従して沈む形になるので、フリーフォールしていくことになります。


オモリは20~40号前後を使うことが多いです。
シンカー形状は根掛かりし辛い、棒オモリやホゴオモリのような形状をしているものが多いですね。
また、オモリ自体にイカを集める効果を持たせた、グローや蛍光系のカラーもあるほか、イカがオモリにアタックするのを防ぐブラックなどのカラーがラインナップされていることも。
アタリがあるけど掛からないという時はオモリにアタックしてきている可能性が高いので、オモリのカラーローテーションも必要ですよ!

オモリグに使用するエギは通常のイカメタルよりも大きい2.5号などがメイン。中には3号、3.5号などのエギを使うこともあります。
カラーはイカメタルと同じく豊富に持っておくことがポイントです。

オモリグの基本の誘いはイカメタルと同じく、誘い上げと誘い下げ。
ポイントはイカメタルよりも大きく竿を動かすこと。

オモリグはキャストで広範囲を探るのも有効
仕かけをカーブフォールさせて、探るのも有効です。
オモリグは仕かけが長いので、イカメタルよりも強めに動かさないと海中ではステイしたままで、エギが全く動いていないという状況になりかねません。


そのためにも、イカメタルよりも大きくシャクる必要があるんですね。
その他の誘い方などはイカメタルと基本的には同じ。エギが大きい分、大きいイカが釣れやすいのが特徴だと言えますね。
手返しのイカメタル、型狙いのオモリグ。どちらで狙うかはあなた次第ですよ~。
胴突き


2~3mの30~50号の船竿にPE2~3号が200m以上巻ける電動リール。オモリは60~80号主体ですが、潮が軽ければ30~40号などの軽いオモリを使うことも。
浮きスッテ、エギは3~5本が一般的でイカメタル、オモリグでは味わえない多点掛けした際の重量感が非常に魅力的。

浮きスッテやプラヅノ、エギなどを3~5本が一般的
エギやスッテ、プラヅノなどをセットしておくツノマットなどがあると非常に便利。

ロッドにタオルなどを巻き付けてツノマットがわりにする人も

胴突きの釣りではイカメタルのような誘い上げ、誘い下げに加えて、電動のスロー巻きが加わる。

電動での誘い上げ

胴突きが有利なのはタナが定まらない時で、仕かけの全長が長く、エダ間(スッテ間の距離)を調節しやすいので、エダ間を狭めてピンポイントにタナを探ることも可能なので、タナが絞れない時はエダ間を広く取り、広範囲を探ることができます。
逆に、浅ダナの手返しの釣りになると、イカメタルの方は針数が少なく、仕かけも短いので手返しがよいので有利ですよ。
胴突きは仕かけ点数が多いので、取り込むときはツノマットに仕かけをセットしながら取り込むと、手返しがよくなります。

以上が船イカ釣りのポイントです。参考にして船のイカ釣りを楽しんでみて下さいね!