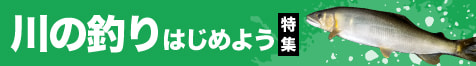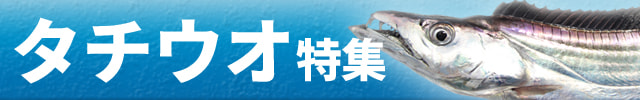西村 豪太(にしむら ごうた) プロフィール
船のテンヤタチウオ釣りは、タックルの進化とともに、その釣り方も旧来とは一変し、全国各地でいろいろな釣法が生まれています。
そして、それがエリアに合った釣り方なら、コンスタントに好釣果を上げることができるのも当然です。
そこで気になるのが、よく釣る人、いわば「名手」と呼ばれる人たちの釣り方。
偶然、同船しても釣座が隣同士にならない限りは、なかなかじっくりと観察できないですよね。
ここでは普段、見ることができないテンヤタチウオの名手の釣りを、タックルから釣り方までを紹介します。
今回は【ジャーク&スロー】の名手、ダイワスタッフの西村豪太氏の釣りにスポットを当てました。
ジャーク&スローとは?

ジャーク&スローとは、文字通りですが、時おりジャークを入れながらスローに巻き上げる誘いです。
テンヤタチウオはタナを探る釣り。基本的には指示ダナ間を下から上へと巻き上げて誘います。
その誘い上げ時に、ジャークをコンスタントに入れて誘い上げていく訳です。

この釣りの誕生秘話を聞くと、「古くは長竿に大きな電動リールでの置き竿スロー巻きが主流だったこの釣りですが、タックルの進化でショートロッドに小型軽量化された電動リールで攻めの釣りをし始めたのがキッカケ。実践を重ねるうちに、もっとアタリをだすためにと、“ラインを張る”、“アクションを足す”という要素をプラスして進化したのが、この釣り。各地で釣果実績も上げることで、このスタイルが自分の釣りとして自信が付きました」とのこと。

ジャーク&スローのやり方
西村氏のジャーク&スローは、特長として電動リールのスロー巻きを必ず入れることです。
だから常に、テンヤは上へ上へと動いています。
これはなぜか?
西村氏に聞くと「ラインテンションを掛け続けることでアタリをしっかりだすため」と言います。

テンヤタチウオの釣りは、誰にでも分かる大きなアタリもあれば、ロッド感度がよくないと穂先に現れない小さなアタリもあります。また、例え感度がよい竿であってもラインが弛んでいれば、名手と言えども小さなアタリは判別し辛いものです。
それを電動リールで巻き続けることによって、ジャークを入れて誘った後もラインが弛む時間を極力短くし、居食いのようなステイでは分かり辛いアタリも分かるようになります。
つまり、ステイなどでは可視化できない、あるいは分かり辛いアタリも、穂先にハッキリとでるようになるんです。
アタリの数が増えれば、自然と掛け合わせるチャンスは増えます。自ずと釣果が伸びる訳ですね。
では、西村氏はどれぐらいの速度で巻き上げているのか。
これはあくまでも目安ですが、通常時や、朝イチ&活性の高い時と、タナが狭い時や活性が低い時では、巻き上げ速度はかわります。
ジャーク&スローの基本の電動巻き速度
ダイワのシーボーグ200JL、同DHで速度3~4。
朝イチや活性の高い時
タチウオの活性が高い時や、高活性が予想される朝イチでは、シーボーグ200JL、同DHで速度5~7。

タナが狭い時や活性が低い時
タチウオの活性が低い時や、なかなか追ってこずにタナが狭い時などは、シーボーグ200JL、同DHで速度1~2。

ポイントの水深や潮の速さによっては、さらに巻く速度が速くなる場合(豊後水道などでは速度10前後のこともある)もありますが、この電動巻きを入れながら、ジャークを定期的に入れます。
※バッテリー環境や釣り場の水深、潮流によっても、数字の表記による巻き上げスピードは変わるので、あくまで参考に。
西村氏のジャークを見ていると、竿の上下幅は小さめ。およそ30~50cmほどでしょうか。


シャクった後にハンドルを巻くのではなく、ジャークと同時にリールを巻き、それを2回、3回と連続で入れます。
そして穂先をピタっと止めてラインを張ります。
イメージでは、スローに上がっていくテンヤがチョンチョンと跳ねるような感じ。
ハンドルの巻き幅は、誘い上げ時はワンピッチ(1回転)、アタリがでれば移動幅を小さく、ハーフピッチ(半回転)、さらには追いが悪いと1/4回転にすることもあるそうです。

タックル&仕かけ

西村氏のタックルは、ダイワの「極鋭タチウオテンヤSP82-182AGS」と「シーボーグ200JL、同DH」。
この組み合わせが、「ジャーク&スローにはベストな組み合わせ」と言います。

アタリをしっかりだすために、常に巻き上げは掛けているものの、やはり穂先の感度は命。

ジャーク&スローのラインを張る効果と、SMT&AGSを装備した超感度の穂先でよりアタリを引きだすことができます。
竿は82調子なので、小さなジャークでも、しっかりとテンヤが動かせるのもポイントです。

リールは、食い渋り時など活性が低い時の超スロー巻きにも対応できるシーボーグ200JL。
MAGMAXモーターで低速域のトルクも十分にあるので、安定したスロー巻きが可能。また、やり取り時に加減速が指1本で調整可能なJOGパワーレバーが装備されているのもポイントです。


テンヤはダイワの「快適船タチウオテンヤSS」や「同40TG」などを状況に応じて使い分けています。
このテンヤは、サルカンを接続するアイの位置により、テンヤの姿勢をかえることができますが、西村氏は基本的に前方のアイに接続するバトルモードで狙っています。
快適船タチウオテンヤSSには、今期新色が4つ発売されましたが、中でも西村氏のお気に入りは昨年度の限定発売で抜群の釣れっぷりを見せてくれたイエローゼブラ赤エラだとか。

攻略パターン

朝イチや高活性の時
ヒットダナを探るため、基本は底から。船長からのタナ指示があればその下限のタナから、ジャーク&スローで狙います。
電動での巻き上げ速度は、60m前後と水深の浅い大阪湾の神戸沖ではシーボーグ200Jで速度5~7で開始。
ジャークを入れるペースは、
5秒電動スロー巻き、
ワンピッチ、あるいはハーフピッチジャークを2、3回、
竿先をピタっと止めて5秒、
再びジャークと、指示ダナの上限まで繰り返していきます。
活性が低い時
活性が低いと判断すれば、電動での巻き上げ速度を落とします。具体的にはシーボーグ200Jで速度1~2。
ジャークを入れるペースも少し間隔を空けるイメージで、スローでソフトな誘いをイメージして釣っていきます。
通常時
巻き上げ速度は、シーボーグ200Jで速度3~4。

要は活性が高いと、ジャーク&スローの誘いも激しく速く、低いとスローにソフトに、を心掛けると、あらゆる場面に対応できます。
西村氏の釣りは、基本は即掛け。

ですが、どんなアタリでも、何から何まで合わせていく訳ではありません。あくまでも掛けられるアタリを即掛け、という意味。
では、どんなアタリを合わせるのか? 主なアタリのパターン別にその対応を解説してくれました。
①穂先を持ち上げるアタリ
→即アワセ
②小さくてもしっかりと押さえ込むアタリ
→即アワセ
③一瞬だけチッとくるアタリ
→合わせずに誘いの速度を落とす。ワンピッチでジャークを入れていればハーフピッチに、ハーフピッチだったなら1/4ピッチに。これは、その時の活性を見て判断
④穂先が震える微妙なアタリ
→ハンドルを巻く。ここでクッと穂先が入れば、即アワセ。これは居食いの時にでるアタリに多いそうで、巻き速度を上げることでテンションが掛かり穂先が入るとのこと

ヒットすれば、基本は電動で巻き上げます。
速度はサイズにもよりますが、小型なら25前後の速度、良型や大型と感じれば速度20前後に落として調整します。
状況に応じたテクニック
大阪湾を例に取ると、夏の神戸沖ではグローがメイン。

グローに今一つ反応が渋い時には紫ゼブラをメインに、水温が下がってくる冬場や、ポイントも洲本沖などの深場がメインになってくるとケイムラも使用。



メインに使用するのはイワシ(大阪湾の場合)。
通常は1尾そのまま使用しますが、小型が多い時や食い渋ってシルエットを小さくしたい時は針もミドルフックのものに、イワシは頭を落として針の軸から少し尾が出る程度に付けます。
また、イワシではエサ持ちが悪い時にはサンマエサも使用します。

エサの付け方で意識しているのは、尾が針の軸より後ろに出ていること。イワシ、サンマエサともにこのポイントに気を付けているそうです。
タナは基本的には船長からの指示ダナで探りますが、指示がなければ底から。
特に、流しかえの1投目はそれまでのタナをリセットして、底から探っています。

アタれば、次の投入時はアタったタナの5m下から誘うのが目安。これは初アタリがでたタナがタチウオのタナではなく、それより前のタナから追いかけてきて、そこでアタった可能性もあるからだそうです。
魚影が濃いと感じれば、指示ダナの上まで誘い上げますが、活性が低い場合はアタったタナの前後2~3mを集中して狙います。
数を釣るためには手返しのよさも大切。
ゆえにオマツリは極力避けたいものです。
その対策として、西村氏はサミングを常用しています。特に、夏シーズンは2枚潮になりやすいので、サミングは必須とのことです。

以上が西村氏の【ジャーク&スロー】についてです。
各個人には自分に合った釣りスタイルがあると思いますが、名手の釣り方を参考にするのも上達への一手。
自分に合う部分だけを取り入れて、自己流に進化させていくのもアリですね。