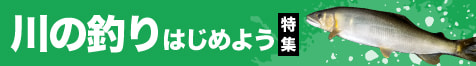食物連鎖を利用して大きな魚を釣る!!
エサとなる小魚から自分で釣って、そのまま大物のいるタナへ仕かけを下ろすのが落とし込み(エリアにより、タテ釣り、アンダーベイトなど呼び名は複数あり)。
仕かけ投入前にエサとなる小魚を針に付けて、タナへ下ろすのがノマセ釣り(エリアにより、泳がせ釣りなど呼び名は複数あり)。

どちらもターゲットは小魚を食べる大きな魚(ブリやカンパチ、ヒラマサなどの青物や、ヒラメやハタ系などの根魚など)になるが、ここではノマセ釣り(泳がせ釣り)のエサの刺し方に注目!!
ノマセ釣りに使われるエサは、主に生きたアジやイワシ、サバなど。


▲日本海の丹後半島エリアでよく使われるカタクチイワシ
そのエサの大きさは、狙うターゲットによって異なるが、近海でのノマセ釣りでの刺し方は、鼻掛け、アゴ刺しなどが多いように思う。

▲鼻掛け

▲アゴ刺し
だが、先日訪れた和歌山県南部堺港の純栄丸では、仕かけに孫針をカットした1本針を勧めていることもあるが、それとは異なる刺し方を推奨していた。

使用したエサは小アジ。
通常の鼻掛けにして、仕かけを用意すると、船長が「その刺し方(鼻掛け)より、外れにくい刺し方があるよ!」と教えてくれたのが、以下の刺し方。
外れにくいと船長が太鼓判!! 鼻口掛け

実演して、その手順を見せてくれた「鼻口掛け」は、
①鼻掛けと同じように針先を鼻に入れる
②そのまま反対の鼻の穴に出す鼻掛けとは異なり、途中で針先の向きをかえ、口の上の硬い所に向けて針先を出す
手順はこれだけ。
だが、これだけで「この刺し方なら、仕かけ投入時や、誘いを掛けたり、仕かけを回収する時にも針がエサから外れにくい」と純栄丸の船長は言う。
ノマセ釣りでは、エサを弱らせないことが重要だが、針がエサから外れないことも重要。

仕かけを下ろす際に、そっと水面に入れてやるのはもちろんだが、この刺し方を行うだけで誘ったり、サミングを緩めに多少早く下ろしても、アタリがでるまでエサが付いているという安心感は、釣り手に心の余裕を与えてくれる。

実際、当日はこの刺し方を行い、アタリがあってエサが取られたりした時や根掛かり時を除けば、回収時に電動の高速で巻き上げても、針はエサから外れていなかった。

エサ持ちのよさは、釣り人がエサに求める条件のひとつだが、この刺し方ならエサを弱らせにくく、孫針を付けているより自然にエサをアピールでき、釣果にもつながる可能性が高まる。
鼻掛け、アゴ刺しもよいが、刺し方のレパートリーのひとつとして、純栄丸船長直伝の「鼻口掛け」を試してみてほしい。